

| 「東海道品川宿」 |
 |
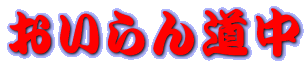
|
 |
| 太鼓が付いている御神輿 (これで鳴らして方向決め等 するらしい) |
地元のお囃子の方々 |
|
| ここでしか見られない、舞台裏!あなたにこっそりお見せしちゃいます。 <舞台裏シリーズ・おいらん編> |
  かつら合わせ(頭の大きさ&額や両サイドの生え際のバランスを見ます) |
|

この長髪を元に床山さんと呼ばれる人が 髪を結います。 |
 浅草にあるかつら屋さん |
  “とのこ”と呼ばれる水化粧をします。 最初に顔に油を満遍なく塗り、白や桃色を重ねていきますが、方法はいろいろあります。 花魁のメークの特徴は笹の葉のような眉(赤色の地に黒で描く) ・目頭と目尻に入る赤み・ほんのり赤い頬・桜の花びらのような唇。 そして手足も白く、背中にも広範囲で塗ります。 あとは顔師さんの腕の見せ所でしょうか。 |
|
 赤い襦袢に赤いけだし。 襟は片方だけひっくり返し粋に見せます。 帯に台を挟み込む。 |
 まな板と呼ばれる前帯をつけます。 |
 後は歩きやすいように裾の位置を決めて、 着付けた着物と掛けをしっかりと固定。 |
 ずれないように所々糸で留めてくれました。 |
 着物は二人がかりで着付けるので、 足の踏ん張りが必要。 |
 当日は、たて兵庫が付いて 花魁のかつらが出来上がってきました。 |
| <舞台裏シリーズ・高張り提灯編> |
 当日しか提灯に触れられないので、 |
|
では、豪華絢爛!おいらん道中の薫りをお楽しみください。 |




| 高張り提灯;後方/大木重美・渡辺利江子・諸戸菜生美・近藤理恵・小林奈保子 前方/佐倉美雪・落合悠莉・平塚純子・片岡明日香・酒巻静 花 魁 ;渡部美穂 |
| 協 力 ;座・芝居屋さん グワィニャオン |
|
貴女もおいらん&かむろ(小学生まで)として参加しませんか? 詳しくは★北品川商店街事務所 電話03−3471−3568まで |
 |
 |
おいらん…漢字で花に魁(さきがけ)と書いて“おいらん”と読みます。 江戸時代の彼女たちの美しさは四季咲きの花の様に美しかったのでしょう。 とりわけ花魁道中は絢爛たるものでした。 |
| 「おいらんまめ知識」・その1 幕府が江戸に移った慶長年間(徳川二代秀忠)に、庄司甚左衛門が幕府に願い出て現在のよしまちべに芸者さんの集まる所を作りました。 よしが茂った原だった事から“よし原”と呼びましたが、明暦の大火で焼失した以降、浅草田浦に移転しこれを“新よし原”と改称し、当時の粋な人が集まる江戸文化のもうひとつの発祥の地となりました。 芸を売るというプライドと格式を持ち、芸事をみっちり仕込まれた芸者と太鼓持ちによる独特のお座敷芸も生まれ、粋なお客様たちに珍重されました。 「おいらんまめ知識」・その2名称編 髪型;立兵庫(たてひょうご)と言う太夫独特のもの。それに16本のクシコウガイという髪飾りを好みで差します。白いものは象牙ですがその時代はあまり輸入されていなかったので、ほとんどが鼈甲だったらしいです。今買うと一式10万円くらいかな、でもこれが当時本物なら一体いくらなのか〜考えると???すごく高いんだろう!ちなみにこのカツラの重さは4キロ。(うっ首が…しかも頭が痛い、血が止まるってな感じです) 着物;前に結んである帯は“まな板帯”と言います。歌舞伎ではまな板の柄を見たら、その役名がわかるそうです。ちなみに私の着物と帯は総重量13キロくらい。 下駄;これは三本歯。片方が2.5キロ。歩く時、8文字(はちもんじ)を踏むと言いますが、片足を軸にして踏んばり、もう一方の足で地面に8と言う字を書くように流します。それを交互に行い、しなりしなりと進むのです。 昔は上方の内8文字(赤いけだしから足が少し見えるあでやかな歩き)、江戸の外8文字(粋でキリっとした凜々しい歩き方)と分かれていましたが、今は粋な外8文字が主流になっています。 |
 |
 |
 |
一言; 毎年9月末土曜日に品川の旧東海道で行われる花魁道中。 元気な女高張り提灯や“かむろ(見習いの少女)”と共に華やかにパレードします。 メイクや着付けも自分で出来るようになったけど、やはりプロの方はすごい。 かつらは辛いが肩貸しのお兄さんが助けてくれる。 皆に混じって楽しくさせてもらっています。 でも何もかもが重いのは豪華と言うのもあるけれど、 当時逃げられないように足かせにしていたと言う話も聞いて、 綺麗な華は捕らわれの身。 そう考えるとちょっぴり悲しい花魁さんです。 MIHO |